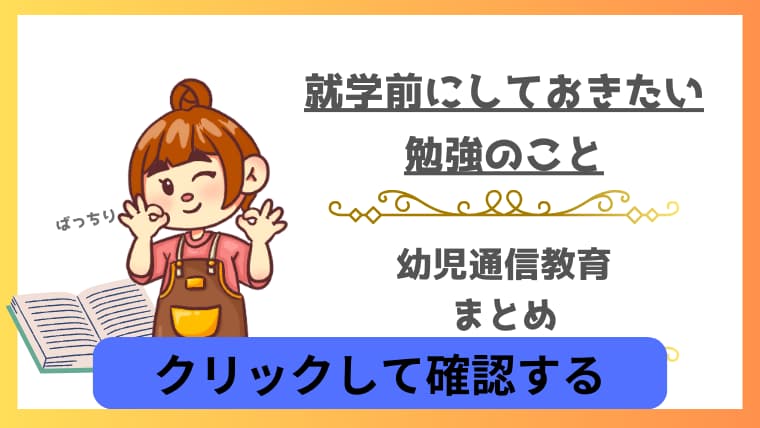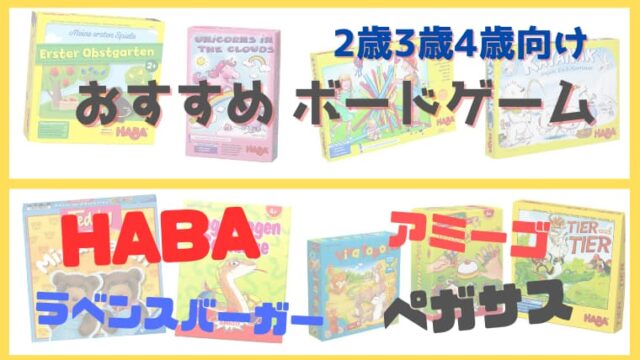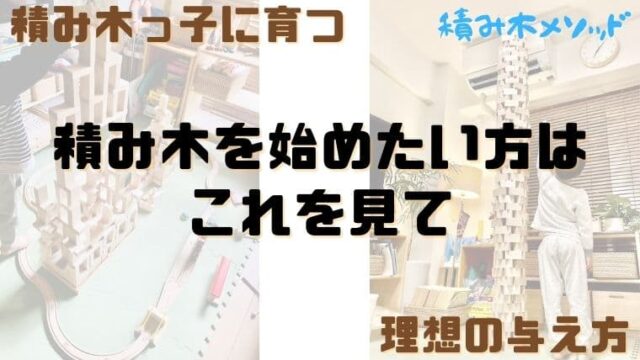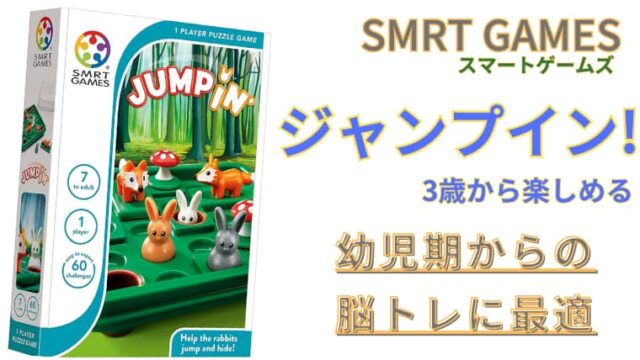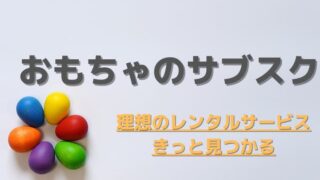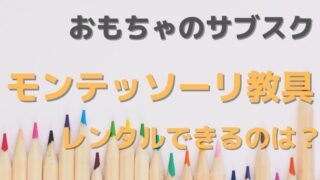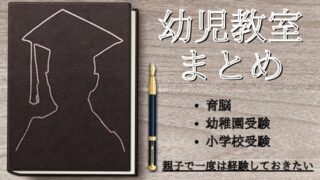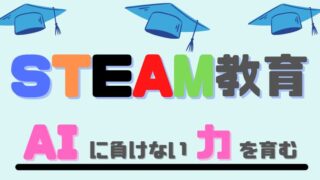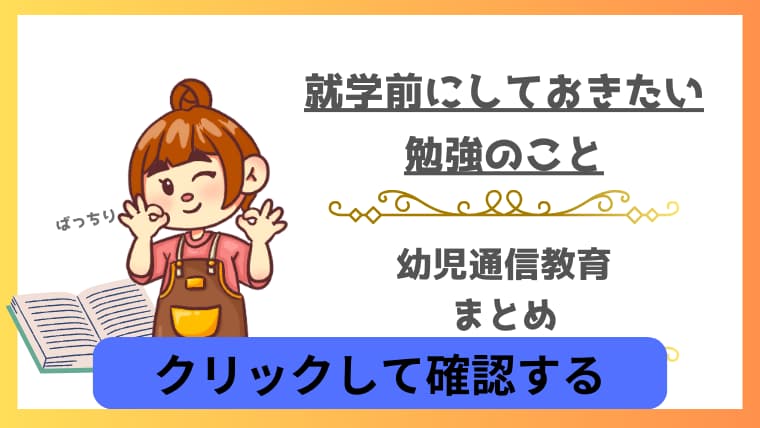積み木遊びのねらいと11の効果を紹介
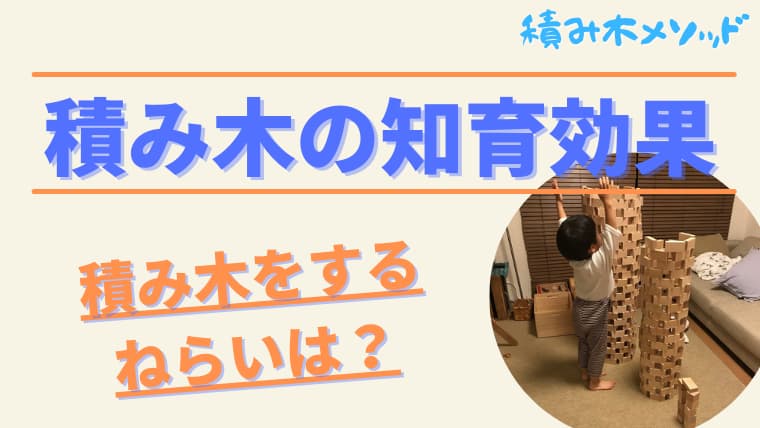
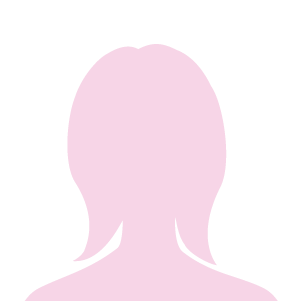
なぜ幼児期の積み木遊びにこだわるの?
ねらいは何?

それは積み木遊びには素晴らしい効果があるからこだわるのです。
もちろんパズルやブロック遊びも素晴らしいものがありますが、積み木はそれらアナログ玩具の中でも育まれる効果がもっとも優れています。
さらに他のおもちゃと併用したり創造性が無限に広がるのも積み木遊びの素晴らしいところです。
積み木を買おうか迷っている方はこの記事を最後まで読んでしっかり積み木遊びの効果を理解してから判断してください。
積み木遊びのねらいと育まれる11の効果

積み木遊びの素晴らしい効果は少なくとも11あります。
- 巧緻性(指先の器用さ)が身につく
- 積み木に取り組むことで集中力が身につく
- 失敗しても挑戦することで忍耐力が身につく
- 作り上げたときの達成感で自己肯定感が身につく
- 考えて積み木遊びをすることで思考力が身につく
- 積み木で育む想像力と創造力
- 積み木で育まれる運動能力がある
- 積み木遊びで自然と身につくバランス力
- 積み木遊びで空間認知能力を身につける
- 積み木は図形の知識が育まれ数学力(算数力)の基礎となる
- 積み木遊びはコミュニケーション力が磨かれる
積み木遊びは少なくともこのような効果をもたらします。
現代では、テレビ・YouTubeなどメディアで遊ぶ子どもが多くいます。
否定をするわけではありませんが、乳幼児期の6歳までは五感が磨かれる外遊びや、アナログおもちゃで遊ぶことが子どもの人間力を形成する上で一番大切です。

それぞれの効果を細かく説明していきます。
巧緻性(指先の器用さ)が身につく
積み木遊びは巧緻性が身につきます。
モンテッソーリ教育の創始者であるマリア・モンテッソーリは「乳幼児期のとくに6歳までは、指先=吐出した脳を使うことが幼児期は大切」と言っています。
積み木を触る、取って掴む動作や、指先の感覚に集中して積み木を積む動作は積み木遊びをしているだけで巧緻性(指先の器用さ)が身につきます。
積み木に取り組むことで集中力が身につく
積み木遊びは集中力が身につきます。
積み木が崩れないようにバランスを考え積む作業は子どもを一時的にフロー状態にさせます。
フロー状態はがむしゃらに集中している状態です。わかりやすく言うと、ぐっと集中して鼻息が荒くなっているときがフロー状態です。フロー状態を何度も経験することで集中力はどんどん身についていきます。
息子は1歳の頃から積み木遊びで「フロー状態」を作ることを私は意識的に行ってきました。
それが良かったのかはわかりませんが、息子が3歳のとき習い事の先生から「息子さんはとても集中力があります」と言われるようになりました。
積み木遊びは息子との経験からも集中力を上昇させると感じます。
失敗しても挑戦することで忍耐力が身につく
積み木遊びは忍耐力が身につきます。
積み木を「積む」ということは積み木が「崩れる」という経験もします。
積み木を積んで目標まで到達できず崩れることは多々あります。
そこで、くじけず、あきらめず、再挑戦することで忍耐力が身についてきます。
乳幼児期は積み木を積んで崩れたら、くじけて諦めてしまうことがあります。ですがそこで挑戦することをサポートしてあげて下さい。その積み重ねが大きな忍耐力を生みます。
積み木が崩れて諦める。これを見過ごすと「積み木は難しい」「積み木は面白くない」に発展してしまいます。親はしっかりサポートしてあげて下さい。
作り上げたときの達成感で自己肯定感が身につく
積み木遊びは自己肯定感が身につきます。
自分で考えて作品を作る過程で、積み上げたものが崩れたり再挑戦して完成した作品は達成感が違います。
やり遂げた喜び、完成した喜び、自分は出来る!喜び。
これらは子どもの自己肯定感を育みます。
考えて積み木遊びをすることで思考力が身につく
積み木遊びは思考力が身につきます。
「どんなふうにしようか」「どうやって積めばつめるか」積み木遊びをするだけで思考力が磨かれます。
積み木で育む想像力と創造力
積み木遊びは想像力と創造力が身につきます。
積み木は基本、まっさらな白木です。
それが子どもの想像力で白木の積み木がいろいろな創造物へ変化します。

例えばこちらのツイートを読んでほしい。
みんなにはこれが何に見える?1個の積木?2歳の彼は『消防車』にみえている。彼には白木の積木1個が『真っ赤な消防車』に見えている。この感性を私はいつまでも大切にしたい。想像と創造を育めるように与えるものを考えていきたい。 pic.twitter.com/D7UnCccibi
— れんし@知育大好きパパ (@Rennshi2) December 17, 2020
積み木で育まれる運動能力がある
積み木遊びで運動能力も育めます。
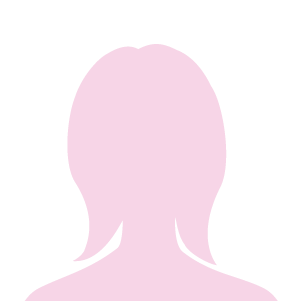
積み木遊びで運動能力?
と思うかもしれませんが積み木で「運動能力」は育まれるのです。
それは先ほど述べたマリア・モンテッソーリが言っていてる「乳幼児期の指先は吐出した脳」ここに関連してきます。
指先を使って脳を刺激することで五感が磨かれます。
乳幼児期の五感のベースアップは身体や精神に大きく影響してきます。
言ってしまえば、乳幼児期に五感のベースアップをしている子どもは、運動能力においても能力を発揮する力が育まれており運動分野の吸収力や発揮力が高いのです。
脳と体を上手に使う神経回路が発達するということです。
積み木遊びで自然と身につくバランス力
積み木遊びでバランス力が身につきます。
おもちゃで自然とバランス力が身につくものは多くありません。
積み木は遊んでいるだけで「崩れるか?崩れないか?」など五感で感じるバランス力が育まれていきます。
積み木遊びで空間認知能力を身につける
積み木遊びは空間認知能力が身につきます。
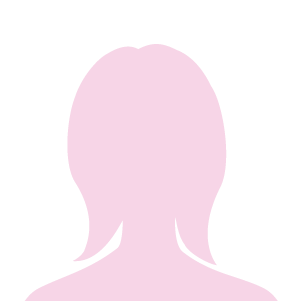
空間認知能力って聞くけど何?
必要性は?
正直、よくわからない親が多いと思います。
空間認知能力は、ものごとを立体的に見る力や、距離感、間隔、方向など、目に見えるものを感覚的に想像し測れる能力です。
生きていくうえで大切なことです。
さらに運動分野でも空間認知能力が高い方は野球選手のイチローなど、スポーツにおいても大切になってきます。
空間認知能力は後天的に伸ばしていきます。
その中で積み木遊びは空間認知能力を育むのに最適な玩具になります。
積み木は図形の知識が育まれ数学力(算数力)の基礎となる
積み木遊びは算数力(数学力)が身につきます。
多くの著書に書かれていますが世の中の成功者には必ず備わっているものが2つあると言われています。
それが「読書家」と「数学力」です。
その1つ「数学力」の土台が積み木で遊んでいるだけで磨かれていくのです。
例えば、直方体の積み木は4:2:1の法則で基尺が決められており、倍や3倍、1/2、1/4などが自然と遊びながら身についていくのです。
さらに積み木を積むとき5cm積み木の上に同じ5cm積み木を積むときに2.5cmずれるとつめないなどの原理なども身につきます。
数学が得意な方はわかると思いますが、数学を伸ばすには必ず図形の知識や感覚がないとつまずきます。
その土台作りに幼児期から積み木遊びで磨いていくのがおすすめです。
積み木遊びはコミュニケーション力が磨かれる
積み木遊びは一人で遊ぶこともできますがコミュニケーションも磨かれます。
親子で積み木遊びをすることで、遊びを通じてコミュニケーションが取れ、会話が苦手なパパでも子どもと自然にコミュニケーションができるのです。
ある日、私の友人のママ友が「パパが娘の遊びに付き合わない」と相談を受けました。
その娘さんがどんな遊びをしているか聞いたところ、3歳でお人形遊びや、粘土遊び、お絵描きが中心でした。
良い遊びをしているなと思ったのですが、パパは苦手みたいで娘さんと遊ばないと悩んでいました。
そこで私が積み木遊びを提案したら2人で良く遊ぶようになったと言われました。
積み木にはこの様に親子を繋ぐコミュニケーションツールとしても力を発揮します。
さらに、息子の話になりますが積み木を通じて友達と遊ぶようになりました。
今日は3歳息子とワクワクアトリエ体験4回目最終日。造形→絵画→造形→積木(本日)。積木どんな感じかな。年長さんとやる積木は面白いのか?気になるところ。積木はコミュニケーションも磨かれる。積み木先生はアトリエでも作品を作るだろうか?今日の感じを見極めて、習い事とするか決める。
— れんし@知育大好きパパ (@Rennshi2) March 6, 2021
このツイート後にアトリエ教室へ通うことになりました。
おうち遊びではないのですが、積み木アトリエ教室で多くの友達と積み木遊びをしながら楽しそうに息子はコミュニケーションをとっていました。
積み木は1人でも遊べますが、友達と遊びながらコミュニケーションをとって作品を作ることもできるのです。
積み木は何歳から?いつから?
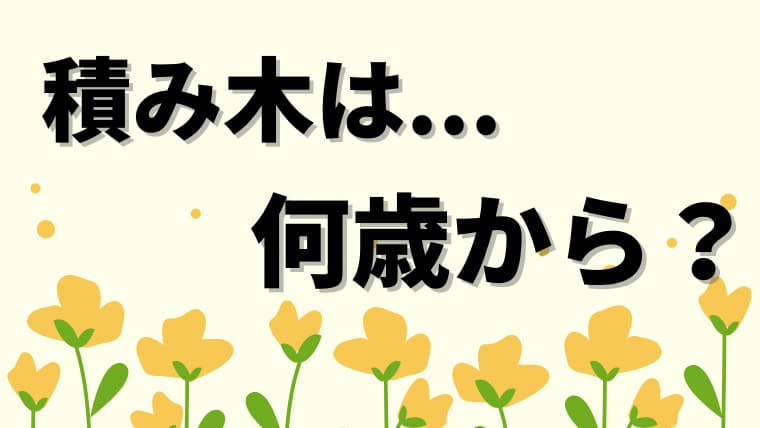
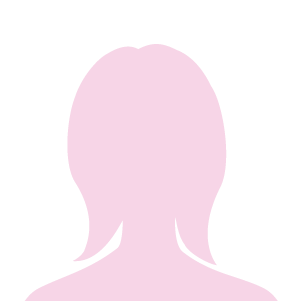
積み木は何歳から?
いつからする?

答えとしては「早ければ早いほど良い」です。
積み木の巨匠であるフレーベルやニキーチンもそのように答えています。
私の息子も0歳から積み木遊びをさせていました。
0歳や1歳は積み木遊びと言えるものではありませんが、積み木に触れてることで自然と積み木が好きになります。
息子に積み木を慣れさせるという点から、0歳息子の近くに積み木を感じさせる環境を意識してきました。
積み木は何歳まで?いつまで?

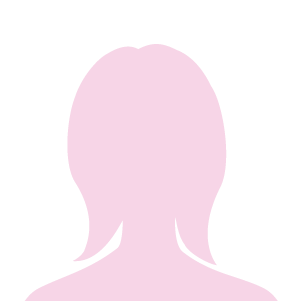
積み木は何歳まで?
いつまで遊ぶの?

小学校低学年までは積み木遊びをします。
以前こちらの記事でアンケート調査をしました↓
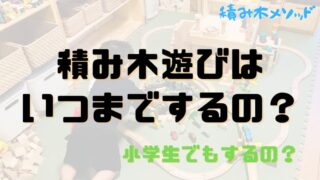
家庭で遊ぶことに関して積み木遊びは「知育に最強」と私は思っています。
積み木遊びでの効果は後で述べさせて頂きますが、ヨーロッパでは中学ぐらいまで積み木遊びをする学校もあるのです。
日本でも童具館の和久洋三さんが「わくわく創造アトリエ」という造形、絵画、積み木を使ったアトリエ教室をひらいています。
息子も3歳からアトリエに行っていますが、アトリエ教室の小学生の作品は大人が驚くほどの創造物を積み木で表現します。
私はこの経験から「積み木はいつまで」という問いに対して終わりはないように感じています。

ではここからはその積み木遊びによる効果を見ていきましょう。
【まとめ】積み木の効果とねらいは人間力の形成
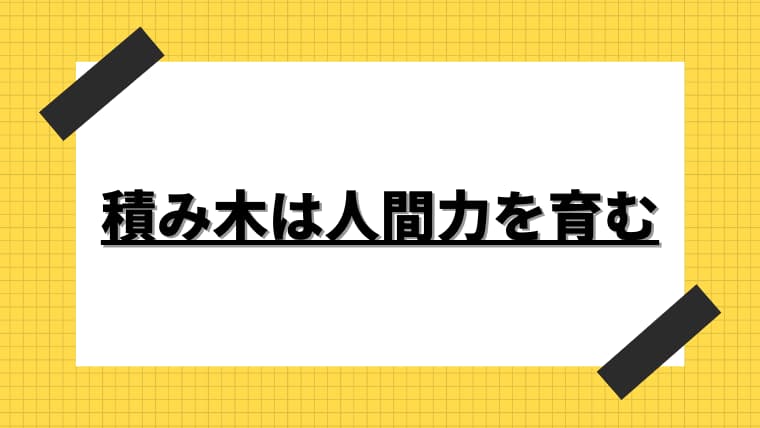
積み木はフレーベルが発案した恩物です。
フレーベルは「遊びを通して自然の法則を身につけさせたい」という思いから積み木は作られています。
子どもたちは積み木遊びの中で、重さ、大きさ、形、重力、大人の反応までも確かめています。
積み木遊びで五感のベースアップ、感性、コミュニケーション力、社会性まで自然と身につけることができるのです。
さらに積み木遊びは無限大に変化する!
積む、並べる、崩すから多様なおもちゃを利用してクーゲルバーン(球の道)などの創造豊かな遊びに発展できます。
他のおもちゃにはここまでの多様性はありません。
- 巧緻性(指先の器用さ)が身につく
- 積み木に取り組むことで集中力が身につく
- 失敗しても挑戦することで忍耐力が身につく
- 作り上げたときの達成感で自己肯定感が身につく
- 考えて積み木遊びをすることで思考力が身につく
- 積み木で育む想像力と創造力
- 積み木で育まれる運動能力がある
- 積み木遊びで自然と身につくバランス力
- 積み木遊びで空間認知能力を身につける
- 積み木は図形の知識が育まれ数学力(算数力)の基礎となる
- 積み木遊びはコミュニケーション力が磨かれる
そして積み木を取り入れるには早ければ早い方が良いと言いましたが、積み木に遅いはありません。
小学生には小学生なりの積み木遊びができますし、球の道のクーゲルバーンやキュボロと言った積み木遊びがあるのです。
積み木購入を検討している方に読んでほしい積み木記事↓
- 子どもが積み木で遊ばない8つの理由を改善したら積み木遊びが好きになる
- 積み木遊びが好きになる年齢別(0歳1歳2歳3歳4歳5歳)の遊び方を紹介
- 【総勢70名以上に聞いた】積み木おすすめの基尺は4.0cmなのか?
- 【保存版】積み木初心者から本格的までおすすめ積み木を紹介
- 積み木とブロックはどっちがいいの?おすすめの理想的な順番を解説
- 積み木好きの息子をもつ親が年齢別(0~5歳)で本気で考えたおすすめ積み木
- 積み木とブロックはどっちがいいの?おすすめの理想的な順番を解説
- 【買ってみた】童具館の積み木「くむくむ」は創造性を育むのに素晴らしい
- 子どもが積み木をいつまでした?気になるアンケートの結果
- 【買ってよかった】積み木マットを童具館のプレイカーペットにした口コミ
- 積み木の遊び方や考え方が理解できる買ってよかったおすすめ本を紹介
【写真・動画大量】積み木作品集はこちら↓
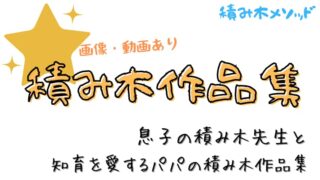
使用している木製レールはこちらで紹介しています↓

使用しているクーゲルバーンはこちらで紹介しています↓